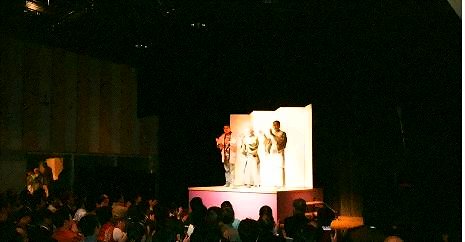« 2008年02月 | メイン | 2008年04月 »
2008年03月25日
<浜松町かもめ亭 川柳川柳喜寿記念会>!
先週の金曜日(3/21)、文化放送・メディアプラスホールにて
「第15回 浜松町かもめ亭 川柳川柳喜寿記念会」が開催されました。
番組は以下の通りです。
<浜松町かもめ亭 川柳川柳喜寿記念会>
立川こはる 『真田小僧』
快楽亭ブラック 『川柳の芝浜』
川柳川柳 『首屋』
中入り
喜寿三本締 川柳・圓丈・ブラック
三遊亭圓丈 『夢一夜』
川柳川柳 『ジャズ息子』
助演をしてくださいました圓丈さんは川柳さんの元弟弟子(六代目圓生門下)、ブラックさんは川柳さんと同じくインディペンデント系(あるいはマイノリティ系)の落語家として知られている御仁。なんともディープな顔合わせの会ではありました。
川柳さんの『ジャズ息子』は『ガーコン』と並び、戦後新作落語の大傑作であり、また川柳さん生涯の代表作です。当夜の出来も喜寿とは思えぬ調子、唄声、台詞が冴えわたり上々の出来でしたが、私はもう一席の古典落語『首屋』にヤラれました。
金に困った男が自分の首を売ることにするという不思議なタッチのこの噺(なんとなく高橋葉介の漫画の世界みたい)時間にして十分にも満たない小品ですが、巧い人が演るとえもいわれぬ味わいがあって大好きです。
川柳さんの口演で、もっとも心にしみ入ったところは、首を売る男がいよいよ斬首される段になり、お屋敷の庭に着座すると一言「もう一遍、世間が見たいんで」と言い、門番にお願いして表通りをちょっと見ます。しかし、何が起きるわけでもなく「へい、有り難うございました。なに、そんなに好きな世間でもなかった・・・」といって首筋をかきあげるくだり・・・。
開けられた門から表を見ている、何もない顔付き、そしてふっと我に返っての述懐に川柳落語の五十数年が見事に結晶されているような思いがしました。
謡曲の『江口』ではありませんが、人の世が「思えば仮の宿」であることをわからせてくれる落語とでも言えばいいのかな・・・浮き世のややこしいあれやこれやのを離れたところから眺めて、サラッと語ってしまう視点が川柳落語の根底にはあるんですよねぇ・・・。
急転直下のサゲまで、最高に贅沢な数分間でした。
(会全体の詳しいレポートは「浜松町かもめ亭 公式サイト」に近くUPされます)
-------------------------------------------------------------------------------
・・・というような感動の高座だったのですが、終演後の打ち上げでは川柳、ブラック両先生が「お○○こ」という日常生活ではあまり耳にすることもない単語をを三十回くらい仰ってくださいましたので噺の余韻もちりぢりになってしまいました!
1・中入り後の高座で、川柳・圓丈・ブラックによる手締めが行われました。
2・打ち上げにて。左から川柳さん、快楽亭正日(ブラック門下の前座。なんと一番太鼓も叩けない)、立川こはる、快楽亭ブラックさん。
3・左からブラックさん、わたし(松本尚久)、笹木美きえ師匠(下座)、石井徹也さん(後方)、川柳さん。まだあまり飲んでないのかな。これだけみると平和そうな雰囲気なんだけど・・。
--------------------------------------------------------------------------------
さて。今後の予定です。
■ 4月24日(木) 第16回 浜松町かもめ亭 柳家の会
出演 柳亭市馬 柳家小袁治 柳家三三 ※ 小袁治・市馬兄弟弟子トーク有り。
■ 5月23日(金) 第17回 浜松町かもめ亭 寿輔・喜多八二人会
出演 古今亭寿輔 柳家喜多八 二席づつ
■ 6月30日(月) 第18回 浜松町かもめ亭 日向ひまわり真打昇進披露会
出演 神田ひまわり改め初代・日向ひまわり(二席) 春風亭小柳枝 瀧川鯉昇
■ 7月7日(月) 第19回 浜松町かもめ亭 立川生志真打昇進披露会
出演 立川笑志改め初代・立川生志 立川志の輔 立川談春
■ 8月29日(金) 第20回 浜松町かもめ亭 怪談噺の会
出演 柳家喬太郎 五街道雲助
前売り情報などは当ブログおよび「浜松町かもめ亭」公式サイトでお知らせをいたします。皆様のご来場をこころよりお待ち申しあげます。
松本尚久(放送作家)
投稿者 落語 : 23:06
2008年03月10日
古今亭志ん生という“荒凡夫”ありき
先日、俳人の金子兜太氏のインタヴュー番組(BSフジ『メッセージ.jp』)に関わったのですが、そのインタヴューの中で、金子氏が江戸時代の俳人・小林一茶の語った「荒凡夫」という心のあり方について、こう仰っしゃっておりました。
金子 (小林)一茶です。
やっぱりあのおじさんにはかなわないっていう気持ちが今あります。
だからあの方は、「荒凡夫だ」なんて言って、平凡で自由な男でいいんだと。
それで、その“平凡”ていうのは、どういう意味かっていうと、自分がその欲望だらけの、
本能の固まりみたいな男だけれども、これはしょうがないっていうような言い方してるから。
作品がそれによって作られ てるから、いい句が多いと。
やっぱり自分が特殊な人間だとか、特殊な才能があるっていう前提での表現っていうのは、
限界がある んじゃないのかな。これ一般的にもどうなんでしょうか?
「自分はもうつまらない普通の人間なんだ」と。
「自分の思いを切実に書けばいいんだ」と。
「みんなと語り合えれば、さらにいいんだ」というぐらいの余裕で書かないと、表現っていうのは
達成できないんじゃないですか。
どうなんですかね?
また、インタヴュー用の資料として拝見した著書の中で、金子氏は「荒凡夫」に関してこういつことも言われています。(石井要約)
業を背負って自由に生きる。
バカはバカなりに、自由に生かしてもらいます、というのが「荒凡夫」の精神。
一茶は、一茶=俳句という存在だから、日常的なくだらなさの中にも秀でた句が生まれる。
本当の俳句というのは、日常が基本です。
こうした言葉を伺って、「ハタ!」と小膝を打ちながら私の思ったのが、五代目古今亭志ん生師匠のこと。特に、金子氏の言われる一茶=俳句を、志ん生=落語と置き換えれば、まさにドンピシャリ!
もっとも、志ん生師に思い至ったのは、このインタヴュー収録の直前、実は俳優の小沢昭一氏が志ん生師について、演劇評論家・矢野誠一氏と対談している文章を読んでいて、こんな一節に出会ったからであります。(『小沢昭一座談⑤』)
矢野
いわゆるアカデミックな学問っていうのはなかったけれど、いみじくもあの人が高座でよく言ってたでしょ、「こういうことは学校ではあまり教えねえ」って。それがすごかったし、虫だとか小動物に対する洞察力にも驚くものがありましたよね。
小沢
だから、文楽は芭蕉で、志ん生が一茶なんだよね。
独得の俳句を詠まれる小沢氏ならではの炯眼、感覚力、比喩の賜物というべきでしょうが、「目から鱗」ってェのはこういうことでありますね。
実を申さば、これまでに数多の方が数多の「志ん生論」を書かれておりますが、それだけではどうにも割り切れないものを私は感じておりました。
「貧乏体験」だとか、「天衣無縫の発想」、「三語楼から受け継いだギャグ(立川談志家元流にいうならイリュージョン)」、「ズボラ」、「酔っぱらい伝説」、私が一番真実の志ん生像を語れる方と思っている小山観翁氏の言われた「一種の完全主義者」「晩年の圓朝作品への傾倒は笑わせるのに草臥れたから」等々のいずれにせよ、、「何か志ん生師の落語をまとめきけれない違和感」をちょっとずつ感じておりました。
そういう違和感を、小沢氏のひと言と、金子氏の語られる「荒凡夫」が吹き飛ばしてくれましたね。
たとえば、志ん生師が生前よく言われたという、「芸なんてェものは年中、出来るものじゃありません。ふだん演っているのは商売ですな」というのが、過去の志ん生論だけでは、どういう感覚・意識から来るのかが、よく分からない。
武智鉄二氏の言われた「過去に、志ん生のような名人路線はありませんでした」にも繋がりますが、「ふだん演っているのは商売ですな」という言葉は、「名人上手というのは、常に切磋琢磨してるもの」という日本の古典芸能感覚と、ハッキリ相対するものがあると思います。「名人上手というのは、常に切磋琢磨してるもの」という芸観に、黒門町の文楽師匠や柏木の圓生師匠は当て嵌まるけれど、志ん生師匠は全然当て嵌まらないでしょ。
それに対して、「日常的なくだらなさの中にも秀でた句が生まれる。本当の俳句というのは、日常が基本です」という金子氏の言葉からは、「ふだん演っているのは商売ですな」と平然と笑っている志ん生師の姿が浮かびます。
志ん生師匠にも、自宅の庭の池の辺りでズーッと池の面を見ている鳩を、居間からズーッと見ていた志ん生師がそばにいたお弟子に、「鳩に気をつけてやんなよ。身投げをするといけねェ」と言ったという逸話がありますが、これが「常に切磋琢磨」だとは私には思えない。
談志家元は著書で「(志ん生は常に)どっかで受けようとしている筈だ」という徳川夢声氏の言葉を引用されていたけれど、それは単なる分析であって、直感に導き出された真実、という切れ味のない意見にしか思えませんでした。
むしろ、一茶の「やせ蛙 負けるな一茶 これにあり」とか「やれ打つな 蝿が手をする 足をする」に近いんじゃないでしょうか。
こりゃ、徳川夢声では知性が邪魔になって分からないやね。
もちろん、「志ん生師がそれを自分の生き方論として自覚していた」なんてことは、私も思いませんよ。自覚しようと努力したりすると、談志家元になっちゃう。
でも、生きて行く中で、志ん生師はそういう風に「自分を肯定しちゃった(居直っちゃった)」のではないでしょうか。
11~12歳で女郎買いをしたり、関東大震災の最中に酒屋へかけつけて大酒を呷ったり、戦争の最中に家族を置き去りにして満州へ行っちゃったり、という無茶苦茶な人生しか送れない自分を、「しょうがない。平凡で自由な男でいい」と肯定しちゃう。
肯定しないと生きちゃいらんないし、肯定できないと自己批判と他人の目が気がかりになって、よくある破滅型芸人の人生を歩んでしまうでしょ。
そこで、「オレはこういう人なの!」と、思い切っちゃった結果の心境が、数多の志ん生伝説に繋がると同時に、『火焔太鼓』から『黄金餅』まで、「人間ってこういうもの。なんでもあり」という、文楽師匠や圓生師匠では性格的に辿りつけない(自分は才能ある落語家である、という自負心が強すぎるというか)、底光する芸の凄さも生んでしまったのではないでしょうか。
皆さんはどう思われますか?
欲望だらけの、本能の固まりみたいな男だけれども、これはしょうがない。
平凡で自由な男でいいんだと。
それで、その“平凡”ていうのは、どういう意味かっていうと、自分がその欲望だらけの、本能
の固まりみたいな男だけれども、これはしょうがない。
「自分はもうつまらない普通の人間なんだ」と。「自分の思いを切実に書けばいいんだ」と。
バカはバカなりに、自由に生かしてもらいます
志ん生師匠の落語には、寝る前や病床で聞くのに、気持ちが楽でいい、という話があります。たとえば、先代勘三郎丈が病床で毎日、『火焔太鼓』を聞いていたというエピソードもあれば、人工透析を受けながら落語のテープを聴いているという三遊亭圓楽師匠は「ことに志ん生師匠の落語はまことにゆったり聴ける。透析向きですね」と仰っしゃっています(『圓楽 芸談 しゃれ噺』)。
これなど、もしかすると、志ん生師の噺か醸し出す、誰にでもある「凡夫心」を力づけてくれる「荒凡夫」のヒーリングゆえかもしれませんよ。
妄言多謝 石井徹也(放送作家)
投稿者 落語 : 23:49
立川談志 十時間

きのう(3月9日・日曜日)、NHKのBSハイビジョン放送で、「立川談志 きょうはまるごと10時間」という番組が放送されました。
http://www3.nhk.or.jp/hensei/program/k/20080309/001/10-1200.html
http://www3.nhk.or.jp/hensei/program/k/20080309/001/10-1900.html
タイトルにあるとおり、談志さんを特集した10時間(!)のスペシャル番組でした。10時間という長尺の番組であり、出演者さん、スタッフも大勢いましたがわたしも部分的にスタッフ(構成)として参加をさせていただきました。久しぶりにテレビのスタジオに行って、ぼーっと何かを待ったり(いわゆる「待ち」)する時間を過ごしました。テレビの、それもVTRもので10時間の番組をつくるというのは大変なことです。ディレクターさんの仕事量ははんぱではなく、放送の二日前まで編集を続け、通しの試写もなく(している時間がない)、昨日無事に放送されました。
そういうわけで、私は番組全体がどういう形でまとまったのか、わからないまま放送を見たのです。
番組では落語もたっぷり放送されたのですが、落語自体よりも、私はドキュメントの被写体としての談志さんがいちばんよかったと思います。
人は誰でも歳をとるので、落語そのものの口調、流暢さは談志さんにしても若い頃のほうがよかったと言えるかもしれません。録音を聴けば分かるとおり、談志さんはまぎれもなく「若い天才」でしたし、私が間に合った50代の頃の高座も、そりゃあ凄かったものです。
今の談志さんには、そういう意味での輝きはもうない。
けど、そのかわりに老いたいまの自分をそのままみせてしまう凄さがあります。
落語はよく出来た芸能なので、歳をとったらとったなりに、安定したところに芸を落とし込んでみせることもできるのではないかと思います。だけど、談志さんはそうしないで「駄目な談志」をそのまま直視する(直視させる)のです。私も含めて、普通の人間というのは、そういう直視には耐えられないものですが、談志さんは迷いながら、苦悩しながら、高座のうえではそれをします。今回のドキュメントでは、高座にあがるまでの談志さんの心の動きを垣間見ることが出来ました。統括ディレクターは制作会社スローハンドの茂原雄二さんです。
私がはじめて談志さんの落語を聴いたのは、高校一年生のときで、日比谷の第一生命ホールで開催されていた「談志一門会」でした。噺は「らくだ」で、まさに衝撃でした。そのときに、前に出て落語をやったのが高田文夫(立川藤志楼)さんと景山民夫(立川八王子)さんで、「道具や」と「時蕎麦」を演じられました。私が放送作家という職業を選んだのは、この一夜の体験があったからです。談志さんの「らくだ」で芸というものの凄さに圧倒され、藤志楼さんの「道具や」でギャグの面白さに、八王子さんの「時蕎麦」で都会的なセンスというものにはっきり目覚めたのです。今回の10時間スペシャルには高田文夫さんの出演コーナーもあり、仕事の場で初めて高田さんとご一緒をさせていただきましたが、いま書いたことを言うと「おれの道具や?ひどいねそりゃ」と軽く流されましたが、その軽い感じが何ともらしくて感無量(我ながら大袈裟・・)でした。
私は学生時代、浅草で「談志を聴く会」という落語会をやっていました。
そのときに談志さんと知り合いになれて、ときには怒られもしましたが可愛がっていただきました。
その後、私の個人的な事情や考えがあり、落語界や談志さんの周辺から遠のきました。(その時期に国立の「談志五夜」や談春さんの真打披露があったので、私はこれらの会に足を運んでいません)
談志さんに再びお目にかかったのは2001年。文化放送ではじまった「立川談志 最後のラジオ」に、ディレクターの首藤さんから構成者として呼んでいただき、談志さんに6~7年ぶりくらいでお目にかかったのです。打ち合わせの場所で、談志さんは私を見ると(談志さんは私が放送作家になっていることをもちろん知らなかったのですが)
「おい!何しに出てきやがった」といい「お前も何かやるのかよ!」と笑いかけてくださいました。
「最後のラジオ」は一年半の放送でしたが、その後もほかの番組や活字の仕事でたびたびご一緒をさせていただいたのは有り難いことです。
今回の10時間スペシャルは、談志さんのいまを伝える充実した内容になっていたと思います。これからまた、談志さんとなにかでご一緒させていただく機会があるのかどうかはわかりませんが、私にとっては今回の番組がなにか大きな区切りのように感じられます。
番組の最後、「居残り」を演じた後に、じっと黙っている談志さんが印象的でした。
そうそう・・・私が国立の「ひとり会」に通っていた頃、まくらの中で、じっと沈黙するときがあり客席もシンとしていました。そんなとき談志さんはきまって「おれ、この沈黙、平気なんだよな」と言ったものです。私が談志さんの落語に引き付けられたのは、むしろその空白の緊迫感にあったような気がします。
とにかく。
談志さん、お疲れ様でした。
松本尚久 (放送作家)
投稿者 落語 : 12:05
2008年03月06日
第14回 浜松町かもめ亭 打ち上げ風景
第14回『浜松町かもめ亭』公演が2月28日(木)、文化放送メディアプラスホールで開かれました。
当日の番組は
『道具屋』 立川春太
『宮戸川』 橘家圓十郎
『風呂敷』 三遊亭遊雀
中入り
俗曲 春風亭美由紀
『愛宕山』 古今亭菊之丞
でした。
今回出演の菊之丞さん、遊雀さん、圓十郎さんは落語協会の前座仲間。キャリアはそれぞれ違うのですが、圓十郎さんが楽屋入りしたときに、遊雀さんが立て前座(前座のトップ)だったので、ぎりぎり同じ時期の楽屋修行を体験している、「前座仲間」ということになるのだそうです。そのせいもあって、この日の楽屋は和気藹々。そんな楽しい楽屋の雰囲気が高座にも現れた会になったと思います。(遊雀さんの「風呂敷」に出てくる夫婦者が「宮戸川」のお花半七の「その後」だったという連携ギャグには大笑い)
また今回は、「かもめ亭」初の色物として俗曲の春風亭美由紀さんがご出演。色っぽい唄と踊り(春雨)で高座に花を添えてくださいました。また前座も初出演の春太(談春門下)が勤めました。
打ち上げで、遊雀さんが「ホール落語と言うよりは、寄席のように全体でひとつの流れをつくる会になっていた。やっていて楽しかった」と仰ってくださったのが印象的でした。
今回の「かもめ亭」は寄席のような暖かさ、やわらかさの横溢する会になったと思います。
さて終演後はホール隣の会議室にて、恒例の打ち上げが催されました。

写真左が挨拶をしてくださっている遊雀さん。時計回りに、菊之丞さん、美由紀さん、前座の春太。遊雀さんは旅回りの体験談など色々と楽しいお話を聞かせてくださいました。
写真右から美由紀さん、菊之丞さん、遊雀さん、寄席文字の春亭右乃香タン、下座の美きえさん。菊之丞さんは「かもめ亭」の数日前、ジャズの北村英治さんのパーティーで、談志師匠と小三治師匠の話し合いという凄い光景を目撃したそうです。
手前に立っているのが立川春太。赤シャツが圓十郎さん。圓十郎さんは前名の橘家亀蔵時代、文化放送「小西克哉のなんだ?なんだ!」(97年~2000年)のレポーターをしていたことがありました。そのころの思い出話で盛り上がりました。じつは私も同番組の末期にレポーターをやっていたことがありんす。
さて3月以降の「浜松町かもめ亭」ラインアップをお知らせしましょう。
■ 3月21日(金) 第15回 浜松町かもめ亭 川柳川柳喜寿記念会
出演 川柳川柳 三遊亭圓丈 快楽亭ブラック
■ 4月24日(木) 第16回 浜松町かもめ亭 柳家の会
出演 柳亭市馬 柳家小袁治 柳家三三 ※ 小袁治・市馬兄弟弟子トーク有り。
■ 5月23日(金) 第17回 浜松町かもめ亭 寿輔・喜多八二人会
出演 古今亭寿輔 柳家喜多八 二席づつ
■ 6月30日(月) 第18回 浜松町かもめ亭 日向ひまわり真打昇進披露会
出演 神田ひまわり改め初代・日向ひまわり(二席) 春風亭小柳枝 瀧川鯉昇
■ 7月7日(月) 第19回 浜松町かもめ亭 立川生志真打昇進披露会
出演 立川笑志改め初代・立川生志 立川志の輔 立川談春
前売り情報などは当ブログおよび「浜松町かもめ亭」公式サイトでお知らせをいたします。皆様のご来場をこころよりお待ち申しあげます。
松本尚久(放送作家)
投稿者 落語 : 23:21